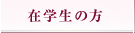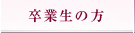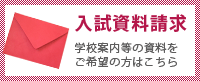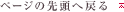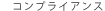2013年02月09日
「百読百鑑」レビュー 『風立ちぬ』堀辰雄 by 17
「風立ちぬ」は堀辰雄の代表作で、結核文学の最高峰に位置する小説。作者の堀辰雄は肺結核を患い、軽井沢で療養することも多く、そこを舞台とした作品を多く残した。
若妻節子が結核を患い、自宅での療養生活から始まる。結核は当時不治の病だったのでサナトリウムという隔離病棟で生活する。院長の診断で療養は1、2年という見通しとなり、節子の病状があまりよくないと院長から告げられる。
八ヶ岳にある高原診療所についた「私」は付添人用の側室に、節子は病室に入院する。院長に病院中でも2番目くらいに重症だと告げられる。9月に、病院中一番重症の17号室の患者が死に、次は節子かと恐怖と不安を感じた。
1935年の10月ごろからサナトリウムから少し離れたところで物語を考え、夕暮れに病室に戻る生活となり、節子との貴重な日々を日記に綴ってゆく。冬になり、12月5日、節子は、山肌に父親の幻影を見た。私が、「お前、家へ帰りたいのだろう?」と問うと、気弱そうに、「ええ、なんだか帰りたくなっちゃったわ」と、節子は小さなかすれ声で答えた。
1936年12月1日、3年ぶりに節子と出会ったK村に私は来た。山小屋で去年のことを追想し、私が今このように生きていられるのも、節子の無償の愛に支えられているのだと気づき、ベランダに出て風の音に耳を傾け立ち続けた。
全編にわたって、ほとんどが心理描写と情景描写、という感じで、あまり動きはないように感じた。やわらかな文章なので優しくも物悲しいような印象を受け、妻節子の容態が悪化し発作が起こる描写が少なく、亡くなるシーンは一切描写されていないことには驚いた。これは、作者自身、そしてその妻が結核を患っていたので書けなかったのではないか、と考えている。一般的には「死のかげの谷」が素晴らしいと言われているが、私は冬の最後の場面が好きだ。いつ死んでしまうのかわからない焦燥感に駆られ、胸が苦しくなったが、感情移入がしやすく感動した。