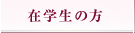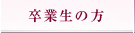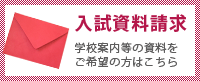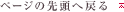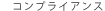2013年01月20日
「百読百鑑」レビュー 『砂の女』阿部公房 by ぴーちこ
20数カ国語にも翻訳され世界中で愛されている阿部公房の『砂の女』である。
主人公は、学校の教師として働く31才のありふれた地味な男性である。作中でも名前で呼ばれることはなく、「男」や「お客さん」などと呼ばれており、どこにでも居る様なごく普通の人間として読者に親しんでもらうことを作者は意図している様に思われる。
彼は、ある日休暇を利用して趣味の昆虫採集を目的に一人で旅行に出掛ける。そこで出会った老人に声を掛けられ、近所の民家に泊めてもらえることとなるのだが、案内された家は想像を絶するものだった。その家の建っているところと言ったら、砂地のくぼみの中にある部落の一番隅で、くぼみの深さはその家が縦に三つ程入るくらいであったから、梯子を使わなければたどり着けない程である。やっとのこと辿り着いた家もひどいもので、壁は剥げ落ち畳はほとんど腐る一歩手前で、歩くと濡れたスポンジを踏むような音をたてた。そこで彼の世話を任されたのが“砂の女”であった。それから女と老人達は手を組み、必死に彼をその部落に留めようとする。村人たちの行動はエスカレートし、逃げ出そうとする彼を瀕死の状態にまでする程だった。そんなところでの生活に耐えられるはずもなく、彼は何度か逃亡を試みるのだが、ことごとく失敗に終わる。そして、彼は仕方なく女と穴の中での生活を共にしていくのだが、その内に、穴の外での自由を求める気持ちより穴の中の生活での充実感のほうが大きくなっていく。そんなある日、突然彼に逃亡の絶好のチャンスが訪れる。しかし、彼は穴の中に留まることを選ぶのであった。
作者はこの作品で、人間は常に憧れというものを抱きながらも自分の置かれた環境に順応するという事を言いたかったのであろうと思う。作者の阿部公房は比喩表現が豊かで、とても生々しいのが特徴である。この作品を読んだときも、残酷な場面が的確に描かれていて心をえぐられたが、もっと深く入り込みたいと思わされた。私自身も、田舎に住んでいたことがあり、店も少なく交通の便も決して良くはなく、今振り返ってみると「よくあんな所で生活できたなあ」と思うのだが、当時は、福岡の方が「人で溢れかえっていて騒がしい」とゾッとしていたことを思い出した。人間は皆現状に満足はせず、常に憧れを抱きながらも、それなりに自分の置かれた環境に順応し楽しく生きているのだと思わされたのと同時に、この貪欲さがあってこそ人類は今日までの発展を遂げたのだとも思った。